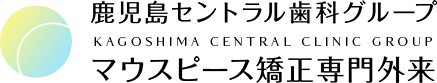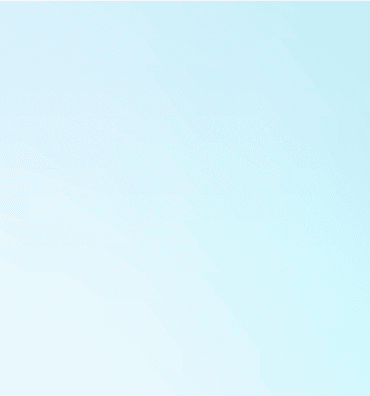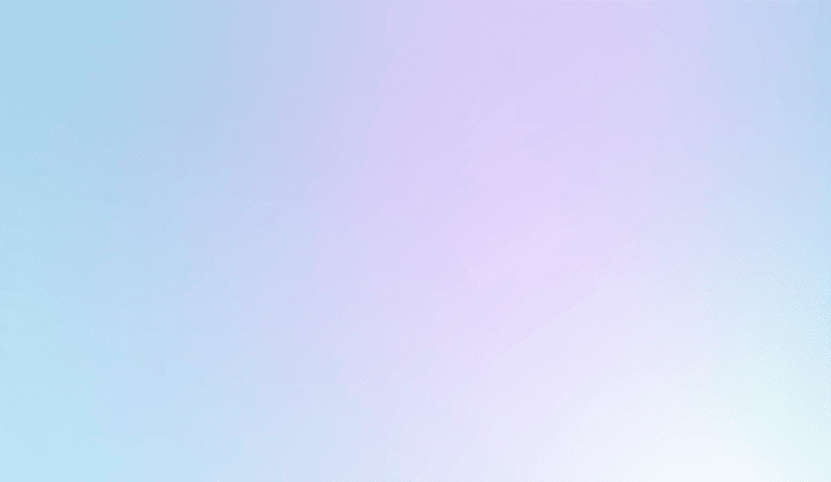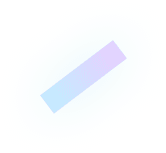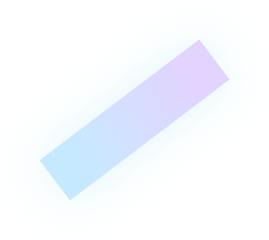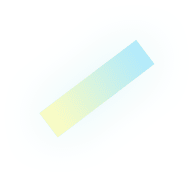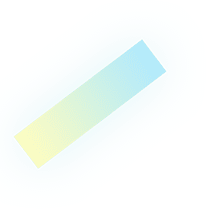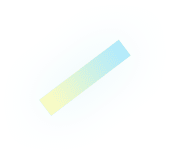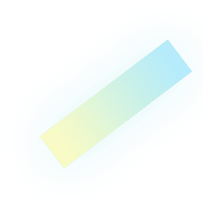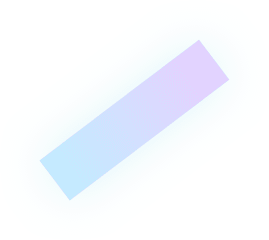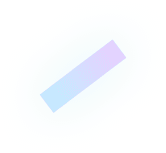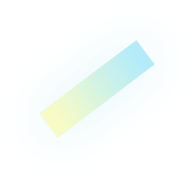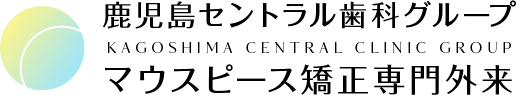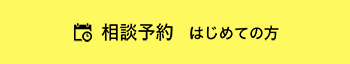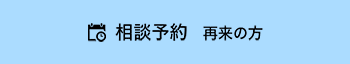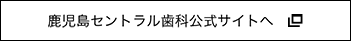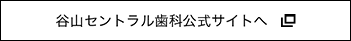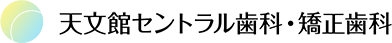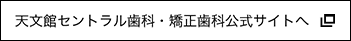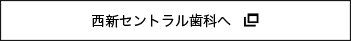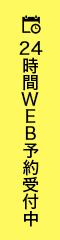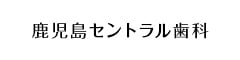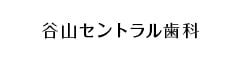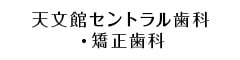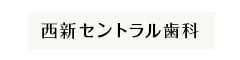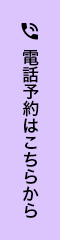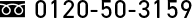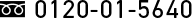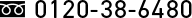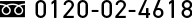後戻りでガッカリしないために!矯正後のリスクと防止策をわかりやすく紹介
歯並びや噛み合わせの改善を目指して矯正治療を受けた患者さまの中には、「きれいになった歯並びが戻ってしまった」という“後戻り”に悩まされる方も少なくありません。時間と費用をかけた矯正治療が台無しになってしまうのは非常に残念なことです。今回は、矯正治療後に起こりうる「後戻り」やそのほかのリスクについて詳しく解説し、それらを防止するための具体的な方法をご紹介いたします。矯正治療後も美しい歯並びをキープするために、知っておくべきポイントをわかりやすくまとめました。
▼矯正後のリスクについて
矯正治療を終えたからといって、すべてが完了したわけではありません。治療後には「後戻り」をはじめとしたいくつかのリスクが潜んでいます。ここでは代表的なリスクとその原因を解説します。
【リスク1】矯正の後戻り
後戻りとは、矯正によって整えた歯並びが、治療前の状態に近づいてしまう現象です。
【原因】
◎保定装置(リテーナー)の不使用・使用不足
矯正治療後には、歯が元の位置に戻ろうとする力が働きます。この力を抑えるために保定装置を使用する必要がありますが、装着時間が不十分だったり途中で使用をやめてしまったりすると、後戻りの原因になります。
◎歯周組織が安定していない状態で保定を中断
歯は歯茎や骨(歯槽骨)で支えられていますが、矯正によって移動したばかりの歯はまだ不安定です。十分な保定期間を確保しないままリテーナーを外すと、歯が動きやすくなります。
◎舌癖や口呼吸などの生活習慣
無意識のうちに歯を押す舌癖や口呼吸、頬杖といった習慣は、歯並びに悪影響を及ぼすことがあります。矯正後の歯にこうした力が加わることで、後戻りを引き起こします。
【リスク2】虫歯・歯周病による歯の動揺
矯正後も油断せず、毎日のケアを続けないと、歯と歯茎の健康を損ねることがあります。
【原因】
◎ブラッシング不足による虫歯
矯正治療中に比べて注意が薄れ、歯磨きが不十分になると虫歯リスクが高まります。虫歯によって歯の構造が変わると、歯の位置に変化が出る可能性もあります。
◎歯周病による歯茎の退縮や骨の吸収
歯周病は歯茎や骨にダメージを与え、歯を支える力を弱くします。その結果、せっかく整えた歯が再び動いてしまうことがあります。
【リスク3】噛み合わせの不安定化
歯並びだけでなく、「噛み合わせ」も矯正の重要なゴールです。
【原因】
◎不十分な治療設計や矯正終了時の微調整不足
噛み合わせがきちんと整っていないまま矯正治療が終了すると、日常の咀嚼や会話によって歯に不均等な力がかかり、少しずつ歯が動いてしまう場合があります。
◎親知らずの萌出による圧力
親知らずが後から生えてくることで、歯列に圧力がかかり、前歯が押し出されるようにして後戻りが起きることがあります。
▼矯正の後戻りのリスクを防止する方法
矯正治療後のリスクを最小限に抑えるには、適切な対策と日々の意識が必要です。ここでは後戻りを防ぐために患者さまご自身でできること、歯科医院と連携して取り組むべきことを解説します。
【方法1】リテーナーの正しい使用を徹底する
リテーナー(保定装置)は、後戻りを防ぐために最も重要なアイテムです。
【ポイント】
◎決められた装着時間を守る
矯正終了直後は、1日20時間以上の装着が必要になることが多く、就寝時だけでは足りません。歯科医師の指示に従いましょう。
◎破損や変形に注意
リテーナーが壊れていたり合わなくなっていたりすると、保定効果が低下します。違和感がある場合はすぐに歯科医院へ相談を。
◎使用期間を自己判断でやめない
自己判断でリテーナーの使用を中止するのは非常にリスクがあります。歯科医師の指示があるまで使用を継続しましょう。
【方法2】生活習慣を見直す
日常の癖や習慣が後戻りの大きな原因になることもあります。
【改善が必要な癖】
◎舌で歯を押す癖(舌癖)
舌が無意識に前歯を押していると、歯並びに影響します。MFT(口腔筋機能療法)などで改善が可能です。
◎口呼吸
鼻呼吸を意識し、口を閉じる習慣を身につけましょう。鼻詰まりが原因であれば、耳鼻科の受診を検討することも大切です。
◎頬杖やうつ伏せ寝
片側だけに力がかかることで、歯列のバランスが崩れやすくなります。
【方法3】定期的なメンテナンスを受ける
治療後も定期的に歯科医院を受診し、歯並びの安定状況をチェックしてもらうことが重要です。
【通院のメリット】
◎後戻りの兆候を早期に発見できる
わずかな変化であっても、歯科医師がチェックすればすぐに対応が可能です。
◎リテーナーの調整ができる
リテーナーの状態を定期的に確認し、必要があれば作り直しや調整を行います。
◎虫歯や歯周病の早期発見
歯並びを安定させるためには、歯や歯茎の健康が欠かせません。お口全体の健康維持にもつながります。
【方法4】親知らずの管理を行う
親知らずが歯列に悪影響を及ぼす前に、対応を検討することも大切です。
【チェックポイント】
◎横向きや斜めに生えている親知らずは要注意
レントゲン撮影で歯の向きを確認し、必要があれば早期の抜歯を検討します。
◎成長期のお子さまの場合は経過観察も大切
親知らずの発育状況に応じて判断していきます。
▼まとめ
矯正治療は、ただ歯を動かすだけではなく、その後の保定期間も含めて「治療の一部」としてとらえることが大切です。後戻りや虫歯、噛み合わせの不具合といったリスクを正しく理解し、保定装置の使用、生活習慣の改善、定期メンテナンスの継続といった対策をとることで、矯正の効果を長く維持することが可能です。患者さま一人ひとりの意識と歯科医院のサポートがあってこそ、美しい歯並びと健康的な噛み合わせは守られます。矯正治療後も気を抜かず、大切な歯をしっかりと守っていきましょう。